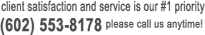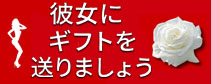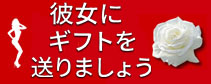アドミラルティ
 1703年にペトロパヴロフスク要塞の要塞が築かれた後、ネヴァ川の河口にさらにもう一つの防衛拠点が築かれました。
この建物は造船所として使われ、後に海軍本部として知られるようになりました。要塞として、海軍本部はその後の市街地開発において重要な役割を果たしました。
1703年にペトロパヴロフスク要塞の要塞が築かれた後、ネヴァ川の河口にさらにもう一つの防衛拠点が築かれました。
この建物は造船所として使われ、後に海軍本部として知られるようになりました。要塞として、海軍本部はその後の市街地開発において重要な役割を果たしました。
当時の軍事工学規則では、敵が隣接する建物に隠れて城壁に近づくことができないように、要塞の周囲に建物を建てることは禁じられていました。
そのため、海軍本部に隣接する地域には建物が建てられませんでした。
そのため、宮殿広場とデカブリスト広場の広い空間は、1870年代に庭園が整備された海軍本部広場と同様に、今も開放されたままです。現在、この広場は作家マクシム・ゴーリキーにちなんで名付けられています。
1705年11月、将来の海軍本部の跡地に土塁が築かれました。
要塞は幾度となく再建されました。現在の建物は石造りのものに建て替えられ、その石造りの建物も次々と再建されました。
1738年、建築家イヴァン・コロボフの設計により本館が再建され、金色の尖塔を戴く塔が建てられました。
19世紀初頭、海軍本部を再び再建することが決定され、建築家アンドレヤン・ザハロフにその建設が依頼されました。
海軍本部の近代的な建物は1806年から1823年にかけて建設されました。建物の上にある立方体の塔は、海軍本部に隣接する広場の建築様式を際立たせています。
塔は、そこに集まる3つの大通り沿いの遠くから見ることができます。正面ファサードの幅は407メートルで、6本柱と12本の柱を持つポルティコに分かれています。

ザハロフは、キャラベル船のような形をした風見鶏を備えた古い尖塔を含む、建物の以前の設計をそのまま残しました。この尖塔は街を見下ろしながら高さ72.5メートルまでそびえ立っていました。
この尖塔は金メッキの真鍮板から切り出されており、長さ192cm、高さ158cm、重さ65kgです。
建物は、当時の著名なロシア彫刻家による56体の大型彫刻、11体のレリーフ、そして350体の型彫り装飾で装飾されています。ファサードの彫刻は、ロシア海軍の栄光という共通のテーマに基づいています。
正面玄関のアーチ上部には、ピョートル大帝によるロシア海軍創設を記念した高浮き彫りがあり、海の神ネプチューンが海を支配する力の象徴であるトライデントをピョートルに手渡している様子が描かれています。
皇帝の隣には、ロシアに訴えかける知恵の女神ミネルヴァが若い女性の姿で月桂樹の下に座っています。ロシアはヘラクレスの棍棒(力の象徴)の上に座り、商業の神が触れる豊穣の角を持っています。
水星が商品の俵の上に降りています。
この高浮き彫りの上、塔の下部立方体の角には、古代の軍師や英雄たち、アキレス、アイアス、ピュロス、そしてアレクサンダー大王が立っています。
 塔の上部立方体の列柱は、28体の彫像(柱の数に対応)で飾られています。それらは四大元素(火、水、空気、土)、四季、四風(南、北、東、西)、そして造船と天文学の神話上の守護神(女神イシスとウラニア)を描いています。それぞれの主題は2回繰り返されています。
塔の上部立方体の列柱は、28体の彫像(柱の数に対応)で飾られています。それらは四大元素(火、水、空気、土)、四季、四風(南、北、東、西)、そして造船と天文学の神話上の守護神(女神イシスとウラニア)を描いています。それぞれの主題は2回繰り返されています。
正面玄関のアーチ道の両側には、高さ11メートルの2つの記念碑群が建てられています。それぞれ3人のニンフを描いたこれらの記念碑は、水、大地、そして空を擬人化した神話の女神ヘカテを象徴しています。
側廊のペディメントには、「労働を祝福する正義の女神テミス」(塔の右側)、「戦場と海上での功績に褒美を与えるテミス」(塔の左側)、「軍功を祝福する栄光」(デカブリスト広場側)、「学問に月桂冠を授ける栄光」(宮殿広場側)の高浮き彫りが施されています。
フェオドーシー・シチェドリン、ステパン・ピメノフ、イヴァン・テレベネフ、ヴァシリー・デムト=マリノフスキーといった当時のロシアの著名な彫刻家たちが、海軍省に作品を寄贈しました。